眼科医インタビュー

子どもの近視、
夜だけのケアで変わる?
累計5,000人以上を
処方した専門医が語る
“オルソケラトロジー”
という選択肢
道玄坂 加藤眼科 加藤 卓次 院長
「最近、うちの子がテレビを見るときに目を細めていて……」
小学生の子どもを持つ親であれば、一度はそんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。
実はいま、世界中で子どもの近視が急増しています。近視は将来的に目の病気につながるリスクもあり、早期の対策が社会的な課題になっています。そのような中で、夜寝ている間に装用することで、日中裸眼で過ごせる視力矯正法「オルソケラトロジー」が注目されています。
今回は、この治療法に20年以上取り組み、世界でもトップレベルのオルソケラトロジー処方実績を誇る「道玄坂 加藤眼科」の加藤卓次院長に、オルソケラトロジーとの出会いから、治療に込めた思い、安全性や効果について伺いました。
どう防ぐ?
子どもの近視進行を止める3つの方法
―― なぜ、子どもの近視がここまで問題視されているのでしょうか?
加藤卓次院長(以下、加藤) 近視が進むと、将来的に網膜剥離や緑内障といった重い目の病気を引き起こすリスクが高まることがわかっています。だからこそ、子どものうちから近視進行を抑制するための対策をとる必要があります。
―― 子どもの近視進行を抑えるにはどんな方法があるのでしょうか?
加藤 子どもの近視進行を抑える方法は、屋外活動で太陽光を浴びること、低濃度アトロピン点眼薬、そしてオルソケラトロジーの3つが代表的です。
オルソケラトロジーは、以前は単に一時的に近視を矯正する手段でしたが、レンズの改良やデータの蓄積により、近視進行の抑制効果があることが明らかになってきました。この事実は、眼科医療においても大きな転換点となる発見だったと感じています。

20年間の診察で実感した
オルソケラトロジーの効果とリスク
―― 20年間の診療で実感されたオルソケラトロジーの効果について教えてください。
加藤 多くの患者さんが、朝レンズを外した直後から視力が明らかに改善したと実感されています。特に、学校生活やスポーツの場面で、裸眼で活動できることによる生活の質の向上を感じる方が多いです。
視力回復のスピードや安定性には個人差がありますが、正しい装用と定期検査を継続すれば、十分な矯正効果が期待できます。また、長期間の経過観察によって、オルソケラトロジーレンズを使用している患者さんは、近視が進行しにくいことを実感しています。
―― 一方で、リスクについてはどのようにお考えでしょうか?
加藤 最初は夜間装用という点でリスクが高いのではないかと懸念していましたが、実際には使い捨てコンタクトレンズと同程度のリスクだと感じています。私は20年間で5,000人以上に処方してきましたが、重篤なトラブルや副作用はほとんどありません。
もちろん不適切な使用による感染症などリスクがゼロではありませんが、限りなく低いというのが正直な印象です。
なぜこの治療を選んだのか?
角膜専門医がオルソケラトロジーを導入した理由
―― オルソケラトロジーを導入されたきっかけについて教えてください。
加藤 眼科専門医として視力矯正に関する新しい治療法には常に関心を持っていました。そんな中、アメリカではオルソケラトロジーレンズ「エメラルド(日本名:マイエメラルド)」がすでにFDA(食品医薬品局)の認可を受け、多くの臨床現場で使われていることを知り、日本でも導入の可能性を感じました。
さまざまな臨床研究のデータや、その信頼性の高さから、当院でもオルソケラトロジーを安心して患者さんに提供できると確信しました。
―― 先生ご自身は、もともと視力矯正の分野に関心があったのですか?
加藤 はい、角膜や屈折矯正が専門で、大学ではレーシックにも関わっていました。視力を矯正する方法は違っても、基本的な考え方は同じで、いずれも角膜の形を変えることで視力を改善するアプローチです。その意味で、オルソケラトロジーは自分の専門と非常に相性が良いと感じていました。
旧来の第1・第2世代レンズは酸素透過性の低さなどから実用性に乏しく、普及していませんでしたが、2000年代に入り第3世代のレンズが登場し、デザインと素材が大幅に改良されたことで、夜間装用でも高い安全性と効果が得られるようになりました。

子どもの方が適応が早い?
オルソの高い継続率と満足度
―― 治療を受ける患者さんの傾向や、ご家族の反応について教えてください。
加藤 近視進行の抑制を目的として、最近は小児の患者さんが非常に増えています。親御さんのほうが積極的なケースも多く、お子さんは最初こそ装用に抵抗感を示すこともありますが、慣れると大人よりも早く上達します。
一度始めると、継続率が非常に高いのも特徴です。3年程度でレンズの作り替えが必要で、決して安価ではありませんが、続ける方が多いのは満足度の高さを示していると思います。
―― 患者さんやご家族によくある誤解には、どのようなものがありますか?
加藤 「オルソレンズによって恒久的に視力が回復する」のはよくある誤解で、継続的な使用が必要です。オルソケラトロジーは、夜にレンズを装用することで角膜の形状を矯正し、翌日の視力を回復させる仕組みであって、レーシックのように視力を永久的に矯正する手術ではありません。装用をやめると、視力は元の状態に戻ります。
患者さんやご家族には、毎晩の装用が必要であることを最初にしっかりご説明しています。

角膜の専門医として
取り組み続けた加藤先生の30年
―― 加藤先生が眼科医になったきっかけを教えてください。
加藤 実は、最初から眼科を目指していたわけではありません。消化器内科、整形外科、眼科と迷う中で、人のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高める感覚器に携わりたいと思い、眼科を選びました。人口高齢化が進むなかで、寿命を延ばすだけでなく、人生の質を上げるためには、眼科医療は重要だと感じたのです。
―― オルソケラトロジーとの関わりを含めて、先生の専門分野について教えてください。
加藤 もともと角膜を専門としていて、医局に入ってからも一貫して角膜疾患に取り組んできました。角膜に関連する内容で論文を執筆したことがきっかけで、米国留学プログラムに選ばれ、ハーバード大学で角膜に関する研究に携わる機会を得ました。
眼科の中で角膜を専門とする医師は全体の1〜2割ほどですが、実際には前眼部から後眼部まで眼全体の診療を行うことが多く、幅広い視点が求められます。「角膜専門だから」という理由で来院される方は多くありませんが、専門的な知見と経験があることで、診療への信頼感につながっていると感じています。米国で最先端の研究に触れた経験は、今の診療にも大きく活かされています。
―― 開業されてから現在までの診療の変化や、オルソケラトロジーとの関わりについて教えてください。
加藤 医局に所属して13年ほど経った頃を機に開業しました。大学では遺伝性角膜疾患など比較的珍しい症例を診ていましたが、実際にそのような患者さんは多くはありません。現在は患者さんの6割以上が緑内障などの慢性疾患を抱えています。
コンタクトレンズ全体の医療機関からの処方数は、ネット購入の普及もあって減少傾向にありますが、オルソケラトロジーに関しては今も安定したニーズがあり、年間1,000名以上のオルソ患者さんを診察しています。すべてが新規ではなく、レンズの寿命に伴う作り替えや継続使用のケースも含まれています。
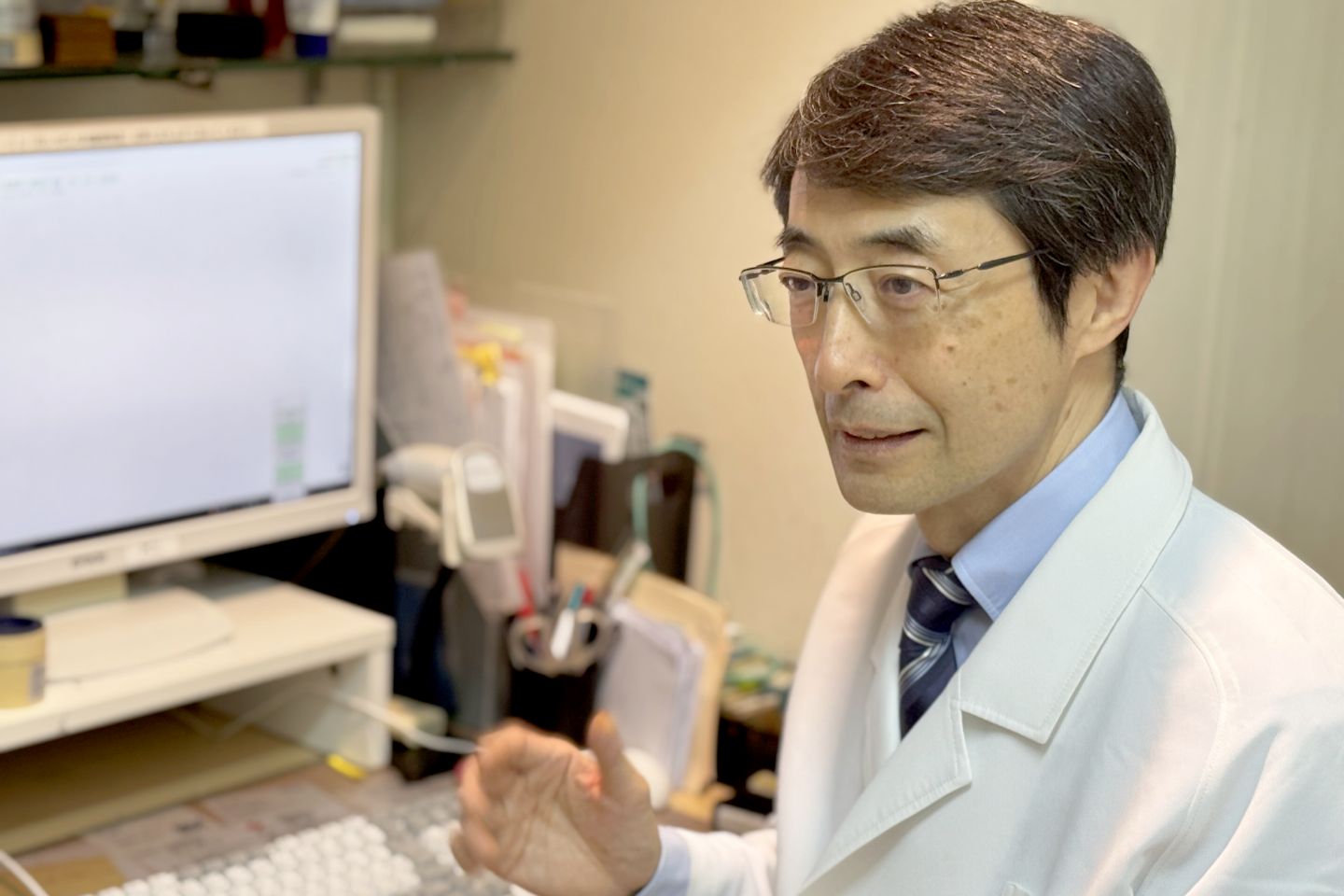
うちの子にも合うの?と思ったら
まずは専門医に相談を
―― 今後のオルソケラトロジーの普及に向けて、どのような課題や期待をお持ちでしょうか?
加藤 医学的にしっかりした根拠に基づく近視進行の抑制方法があるということは非常に画期的なことなのですが、最大の課題は、残念ながらまだまだこの治療法があまり知られていないことです。
近視は、将来的に重篤な目の病気につながる恐れがあるからこそ、子どものうちからの対策が重要です。これは、個人の健康を守るだけでなく、社会全体にとっても重要なテーマになると考えています。
実際、オルソケラトロジーを導入する眼科は少しずつ増えており、これはとても良いことだと思います。私自身も、一医院の枠を超えて、全国に信頼できる専門医が増えていくことを願っています。正しい知識が広がり、必要なご家庭に届くことで、もっと多くのお子さんの視力を守れるはずです。
―― この記事を読んで関心を持たれた保護者の方へ、最後にメッセージをお願いします。
加藤 近視の進行は、放っておいて良くなるものではありません。ちいさな子どもを持つ親御さんには特に、エビデンスの確立された対策方法があることを知っていただけたら嬉しいです。まずは信頼できる専門医に相談することが大切だと思います。
■加藤 卓次 プロフィール
<経歴>
- 1991年 順天堂大学医学部卒業
- 1995年 東京大学大学院 研究員
- 1999年 米国ハーバード大学眼科 フェロー(角膜・屈折矯正手術部門)
- 2001年 順天堂大学医学部 講師(眼科学講座)
- 2004年 道玄坂 加藤眼科 開院
<資格>
- 医学博士
- 日本眼科学会認定 眼科専門医
<受賞>
- ボシュロムリサーチフェロー賞(マサチューセッツ眼科耳鼻科病院)
- 米国眼科学会 最優秀ビデオ賞
道玄坂 加藤眼科
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-3-2 大外ビル5F |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6415-3190 |
| 診療科目 | 眼科 |
| 診療時間 | 10:30〜12:30/14:00〜19:00 |
| 休診日 | 年末年始・ビル休館日(年4回) |
| アクセス | 渋谷駅 5-1番出口目の前 |
近視でお悩みの方は以下のページから、お近くのオルソケラトロジーレンズを取り扱っている眼科を探しましょう。
取扱眼科検索はこちら

